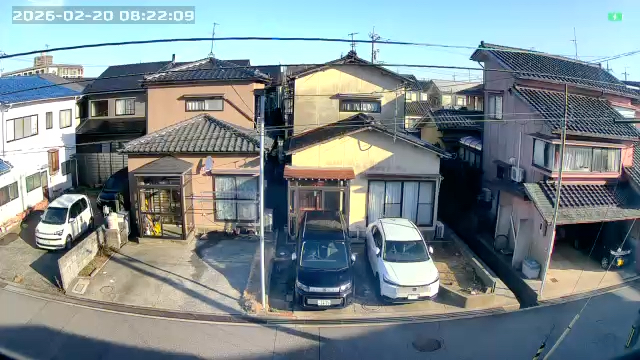今日は、2月23日(月)。
みなさんご存知の通り、天皇誕生日で国民の祝日です。
ところで、”国民の祝日” って何日あるんでしょうかね…
そう思って内閣府のサイトで確認したところ、国民の祝日は以下の16日でした。
・ 1月 1日 元旦
・ 1月12日 成人の日
・ 2月11日 建国記念の日
・ 2月23日 天皇誕生日 ← 今日はこの日
・ 3月20日 春分の日
・ 4月29日 昭和の日
・ 5月 3日 憲法記念日
・ 5月 4日 みどりの日
・ 5月 5日 こどもの日
・ 7月20日 海の日
・ 8月11日 山の日
・ 9月21日 敬老の日
・ 9月23日 秋分の日
・10月12日 スポーツの日
・11月 3日 文化の日
・11月23日 勤労感謝の日
上記に加えて以下の2日が、祝日法によって休日になっています。
・ 5月 6日 振替休日
・ 9月22日 国民の祝日
ということで、2026年の祝日/休日は18日でした。
いやー、案外いっぱいありますね。
この中で、土曜日/日曜日を含めて連休になるのは、
・1月10日〜12日
・2月21日〜23日 ← 今日はここ
・3月20日〜22日
・5月2日〜6日
・7月18日〜20日
・9月19日〜23日
・10月10日〜12日
・11月21日〜23日
の8回。
「土曜日あるいは日曜日もお休みでなく、私は出勤だ」…
という方もおられるでしょう。
とりあえず、”多数派” と思われるパターンとして、土日を含めて調べてみました。
悪しからず…
2026年では8回ある連休のうち、今日の時点で2回目までが終了。
それでもまだ、この先6回の連休が待っています。
みなさんは、その残った6回の連休で何かイベントを企画していますかね?
連休と聞くと、家族で出かける旅行/ドライブ、友人たちとのバーベキュー…など、色々なイベントが思い浮かびます。
もちろん、久しく行っていないロードバイクでのライドイベントも…
「さて、今年はどんなイベントを企画しようかな」
そんなことを思った、この日の私でした。