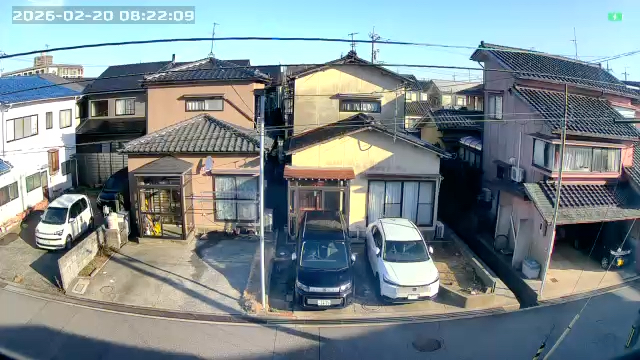今日は、2月21日(土)。
昨日 20日(金)、私は、妻と一緒に映画を見に行きました。
その映画は…
この日が公開初日となる、木村拓哉主演の『教場 Reguiem』。

妻から、
「映画を見に行こう!」
と誘われて見に行ったこの映画。
上記の経緯があり、この日のチケットはすべて妻持ち。
予約する際、妻は
「どの時間帯で予約すれば、ゆったりできるか」
を散々迷ったあげく、平日の午後一番の時間帯を予約。
「これならゆったりできるはず」…
そう思っていたのですが、その予想は裏切られました。
改札開始と同時に入館した私たちは、ほぼ一番乗り。
さっそく予約したシートに座ってあたりを見回すと、2割程度の席が埋まっているのみ。
最初は、
「こりゃガラガラだな」
と思っていました。
しかし、平日の午後にも関わらず、後から後から人が入ってきます。
若いカップル、女性の友人組、私たちと同年輩(or 先輩?)のご夫婦と思しき方々で、9割ほどの席が埋まってしまいました。
フジテレビのドラマでは、これまでも、
・踊る大捜査線
・SP
などで、ドラマの続編を映画として公開しており、それぞれ注目を集めた実績がありますね。
「さすが話題の映画だけあって、結局満席近くになるんだな」…
そんな感想を持ちました。
肝心の映画ですが、私はちょっと入り込めない感じでした。
というのも、私はテレビの教場シリーズを見ておらず、ベースとなるストーリー/伏線等もまったく知らない状態。
そんな人が、劇場公開の映画のみを見て楽しむには、ちょっとギャップがある…
というのが正直な感想でした。
また、私が映画というものから連想する ”画面の印象” とは、ちょっと違うような印象もありました。
やはり、どことなく ”TVドラマ” というイメージ…
でしたかね。
これに対して妻は、テレビのドラマも含めてすべてチェック済み。
そんな背景もあり、もう映画が始まると同時にストーリーに没入。
「私はとっても楽しめた!」
…そうです。
映画への ”没入感”。
これ、私がその映画を評価するときの、かなり大事な要素になります。
前回、私が妻と一緒に見た映画は『ミッション:インポッシブル』(「不可能な任務…」)。
このときは、前編となっている前作映画を、妻&次女と共に私も自宅で予習。
そのおかげで、私も冒頭から映画に没入できました。
つぎに映画に誘われたとき、もし何かの続編という位置付けの作品だった場合は、ぜひ前作等の予習をしておきたい…
そう思ったこの日の私でした。