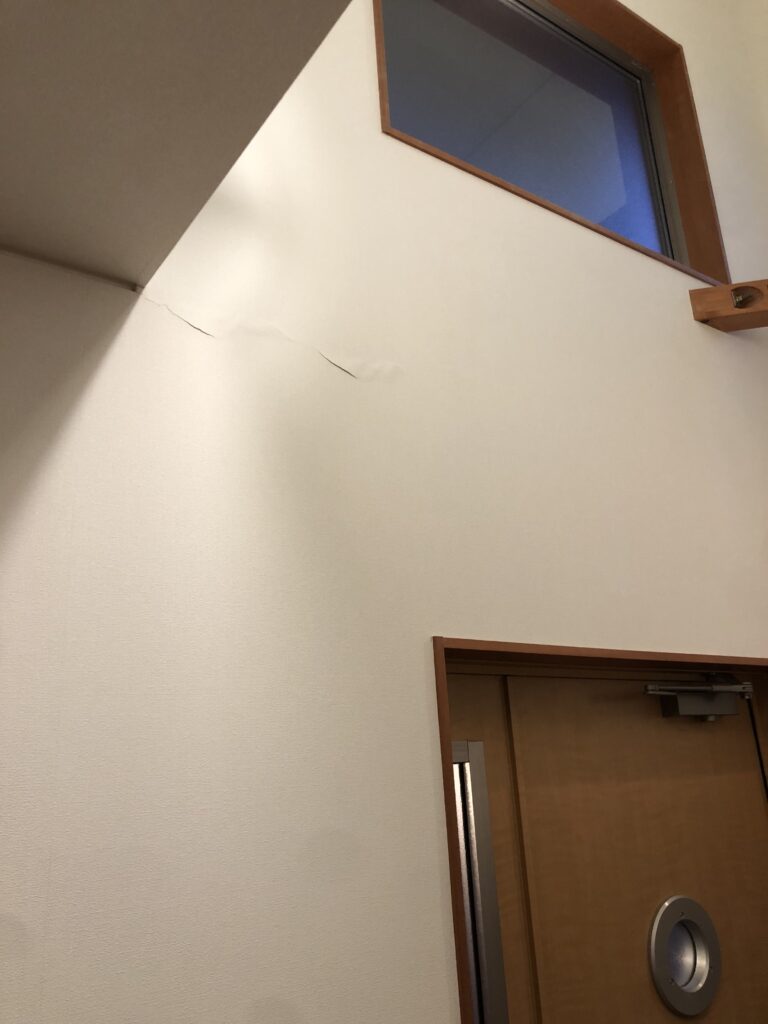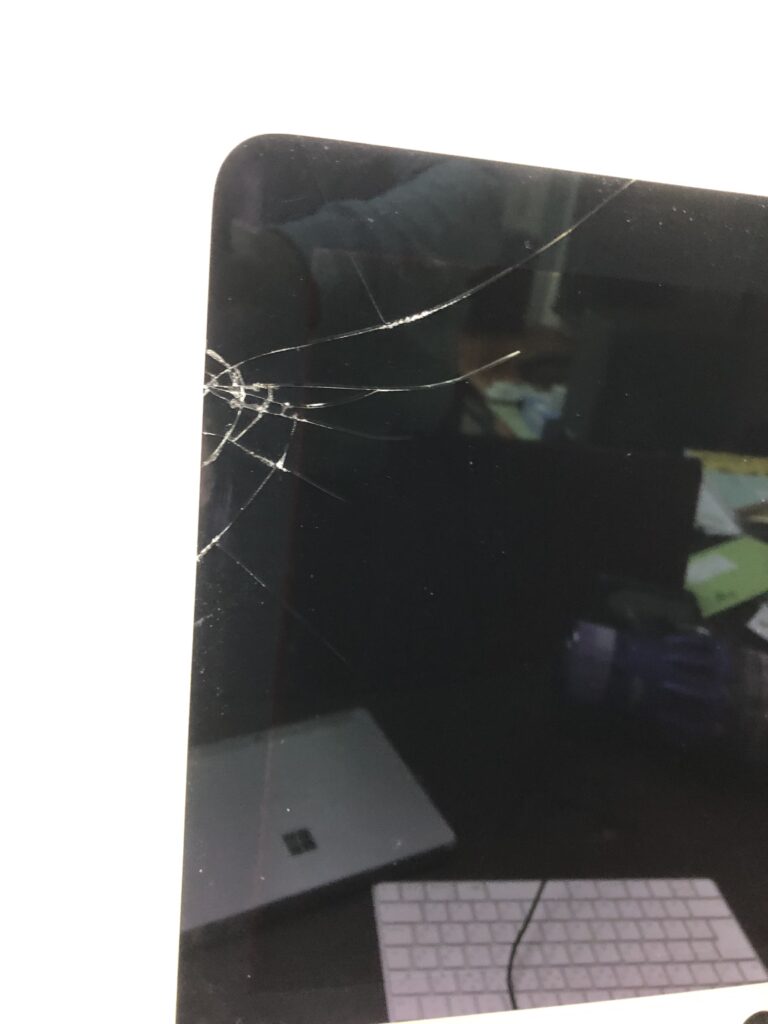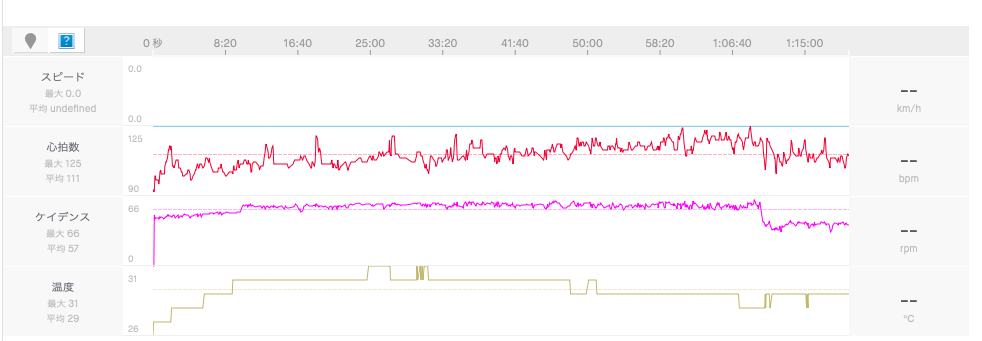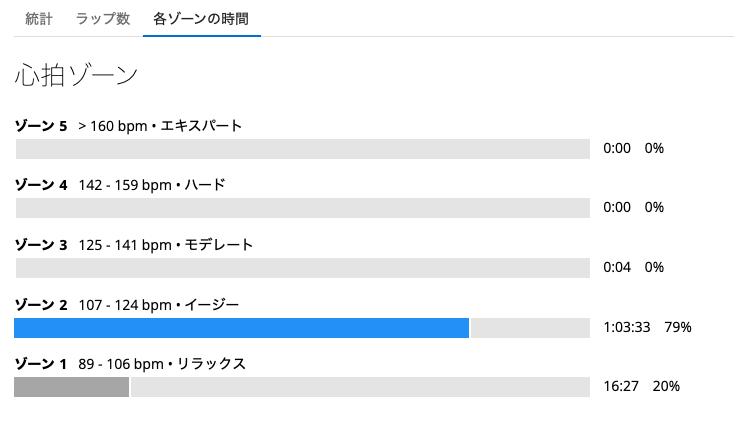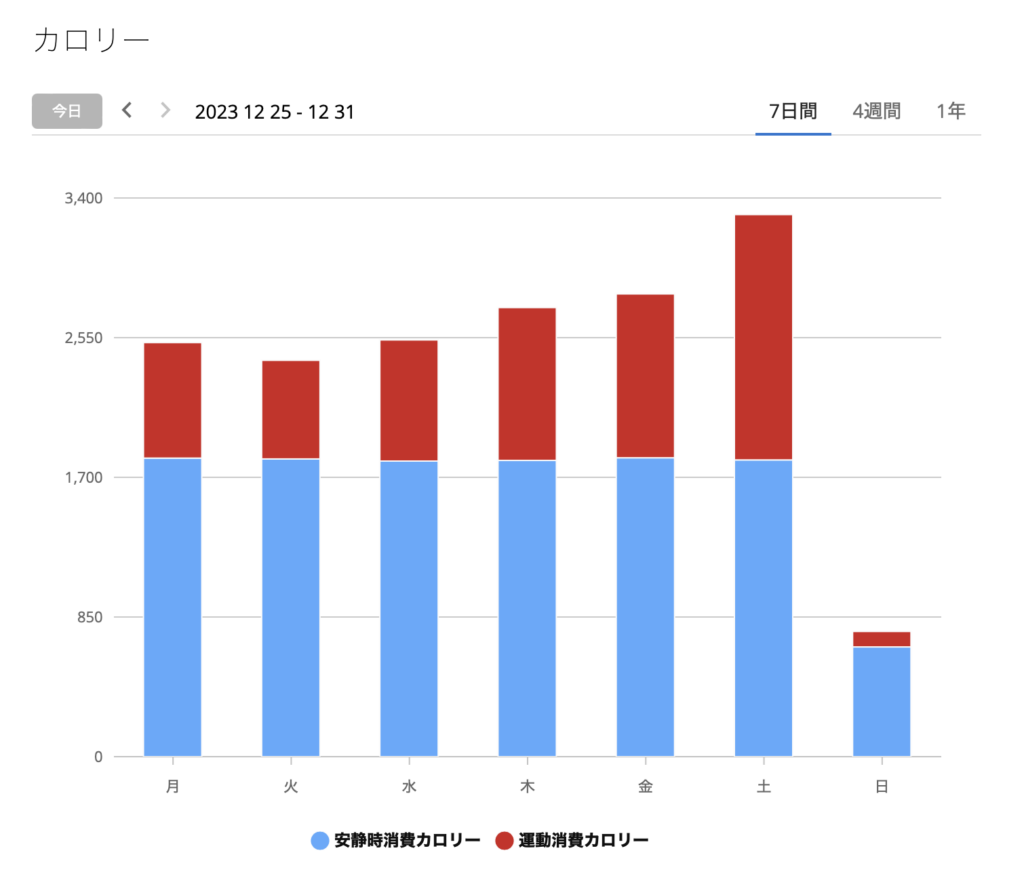今日は、1月4日(木)。
私は昨日の3日(水)から仕事を開始しましたが、正月三が日が終わった今日から、お仕事が始まる方が多いのではないでしょうか。
社会人である次女も、今日が仕事始め。
昨日までののんびりした生活に区切りをつけ、朝6時半には起きて朝食を食べ、7時半前に出勤していきました。
一方私は、昨日から事務所に出勤しています。
ただし昨日は、まだ少々乱れていた棚および机の上を片付けたり、書庫で倒れている書類等の片付け、棚から落ちた際に割れたCDケースの破片を集めて捨てる…等の整理整頓が中心。
それらがひと段落してちょっと一息入れてから、いよいよ本格的に作業を開始します。
本格的に作業開始…とは言っても、まずはガラスが割れたiMacの電源を入れ、液晶の表示に影響が及んでいないかをチェックします。
幸いなことに内部の液晶は割れておらず、画面が表示される機能そのものには影響が及んでいません。
とりあえずiMacで作業する分には支障はなく一安心しました。
しかし、ガラスが割れている左上の箇所は、やはり画面の表示が見にくい状態になってしまいました。
本当なら買い替えたいところですが、必要な費用を考えるとちょっと躊躇してしまいます…
動画編集作業の遅さに限界を感じ、2020年に買い替えたiMac 2019(「道具の入れ替え/更新」)。
そのiMacよりも、ダメになったバッテリーをサードパーティのものに交換して(「りんご 電池復活」)、なんとか使い続けているMacBookAir(Mid-2013)の方を先に買い替えたいところ。
さてどうしたものか…
こわれたiMacの前面ガラス。
見にくい状態を我慢して使うか、思い切って買い替えるか。
こわれた ”ガラスの林檎”をどうするか。
ちょっと迷ってみようと思います。
追伸
松田聖子さんの「ガラスの林檎」。
先日の投稿では、中森明菜さんの曲には名曲が多い…と書きました(「ブロンド…」)が、それに負けずに素晴らしい曲が多いのが、松田聖子さんの曲。
この「ガラスの林檎」という曲は、作詞が松本隆さん、作曲が細野晴臣さんであり、松田聖子さんのその他の曲と同じように、超有名な方々による作詞/作曲の曲です。
「ガラスの林檎」🎵
蒼ざめた月が東からのぼるわ
丘の斜面ではコスモスが揺れてる
目を閉じてあなたの腕の中
気をつけてこわれそうな心
ガラスの林檎たち
私自身は、この歌は、歌詞や曲のイメージに対して、松田聖子さんの声では「甘すぎる」…という印象を持っていました。
しかし今日、3年ほど前に開催されたコンサートで「ガラスの林檎」を歌っている動画を見ました(聴きました)が、曲がリリースされた頃とは違って「甘すぎる」という印象はなくなり、逆にちょっとした「重み」のようなものも感じました。
上記の動画を見た後、シングルでリリースされた曲そのままを聴いて比べてみました。
私は、「甘さ」は無くなったことで、コンサートでの歌の方が良い印象を受けましたが、その代わり歌い方のちょっとした「クセ」が多くなっているような気がしました。
また、リリース当時の歌からは「初々しさ」を感じるのですが、コンサート版からは「貫禄」を感じます。
リリースされてから40年以上経っていますから、まあ、それは当然なのかもしれませんね…
40年ほど前にリリースされた日本の歌謡曲。
それらをあらためて聞いてみるのも、悪くないものです。