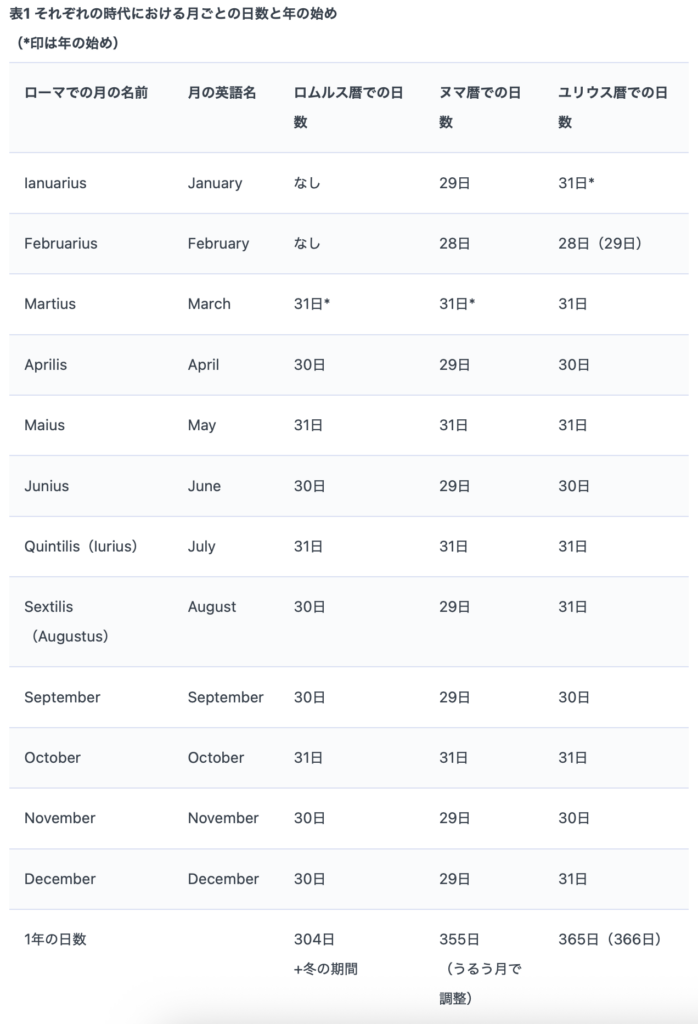今日は、2月26日(木)。
高校もの卒業式を控え、このところ長い長い春休みに入っている長男。
彼は今、普通自動車免許(MT車)を取得するために、毎日自動車学校へ教習を受けに行っています(「誰もが通った…」)。
先日の投稿では、
「入校したのはいいけれど、教習の予約もろくにしていない」…
という趣旨のことを書きました。
しかし、いざ教習に行き始めると違ってきました。
予約していた初日の教習終了後に、翌日の教習枠に空きがあることを自主的にチェック。
元々翌日は1枠のみの予約で、ちょっと効率が悪い。
なので、彼はその空いていた枠を確保して、翌日は2枠を予約してきました。
それ以降、教習を受けに自動車学校に通うたびに空き枠をチェックして予約するようになリました。
受講枠を効率的に予約する工夫により、このところ開校されている日は、彼も毎日自動車学校に通うようになっています。
いやー、親バカかもしれませんが、これは大きな進歩ですね。
昨日 25日(水)の午後も、長男は自動車学校に通っていました。
晴れた日、彼は自転車で自動車学校に通うのですが、このところ、やや天候は不順。
このため、一昨日は妻に送り/迎えを頼んだ由。
ただし昨日は、受講する時間枠の関係から、お迎えが夕食前の時間になる…
ということで、私が長男のお迎えをするように、妻から頼まれていました。
受講終了の少し前に自動車学校の駐車場に到着。
そのまま長男が来るのを待っていると、ちょっと微妙な顔をして長男が車に乗り込んできました。
乗り込んできた途端に、
「今日は、講師の人に、ちょっと怒られた」…
と言います。
「おっ、そうか。どんなことで怒られた?」
私がそう聞くと、
「講師の人から、『自己流で操作するのではなくて、ちゃんと学科の本に書いてある内容を理解しておくように』って言われた」…
と、長男。
どうやら、車に乗ってから発進するまでの一連の操作手順が、自動車学校で教えている(教則本に書いてある)内容と、長男が行った操作手順が違っていたようです。
そのため、講師の方が長男に ”一連の操作手順” について質問をしたのですが、この質問に長男が上手く答えられず、そこを講師の方から指摘された…
と、こんな状況だったとのこと。
あー、確かに、決められた操作手順がありましたね。
(1)後方を確認してドアを開ける
(2)ドアを閉めたらドアロック
(3)座席位置の調整(ブレーキとクラッチのペダル)
(4)ルームミラーの調整
(5)シートベルト
(6)ブレーキ/クラッチを踏んでニュートラル&サイドブレーキ確認
(7)エンジンスタート
(8)ドアミラーの調整
そして、それに引き続いて発進は、
(9)安全確認
(10)発進の合図(右ウインカー)
(11)ブレーキ/クラッチを踏んだままギアを1速に
(12)サイドブレーキを解除
(13)再度安全確認
(14)アクセル/クラッチを操作してスムーズに発進
…と、こんな感じですかね。
シート位置の調整やら、ルームミラー&ドアミラー等の確認やら、エンジンスタートのタイミング…等々。
なんか、面倒くさかったような記憶があります。
まあ、それぞれの操作の順番が決められていることには、ちゃんとした理由があります。
その理由まで含めて理解をしているか…
そこですかね。
最近の自動車学校は、実際に車に乗る技能教習については、まさに自動車学校に行く必要があります。
しかし学科の講義を受講するのは、すべてネットで該当ビデオを見る形式になっているようです。
「この ”学科の講義方法の違い” が、理解度の違いに影響しているんじゃないか」…
昭和生まれの私は、
・決められた時間に教室で行う講師との対面講義
に比べ、
・自分の都合に合わせてスマホでビデオを見る講義
では、受講した内容が ”頭に残る度合い” が少ないんじゃないか…
そんな風に感じてしまいます。
IT技術/ネット環境の進化に伴って、どんどん世の中が便利になっていきます。
外に出なくても会議が開催できますし、講義を受けることもできます。
しかしこれって、”良いこと” ばかりなんでしょうかね…
IT技術/ネット環境の進化によって、いずれ車の完全自動運転が実現する社会が実現するでしょう。
それは世の中にとって ”良いこと” であることは間違いありません。
しかし、それが
「私にとって幸せか?」
という点に疑問を感じる…
そんなことを、以前の投稿に書きました(「それって幸せ?…」)。
色々な人が教室に集まって、講師の話を聞く。
いろんな人が受講していて、かつ対面の講義で、たまに講師の人が質問してきたりもする。
そんなこんなで、少し緊張もするけど、集中して講義を受けることができる。
その結果、内容が頭に残る度合いも高い…
でも、新型コロナが流行して以降、自動車学校の講義は変わってしまい、もう元に戻ることはないんだろうなぁ…
昭和な古い感覚なのかもしれません。
…が、ちょっと残念な気分になった、この日の私でした。