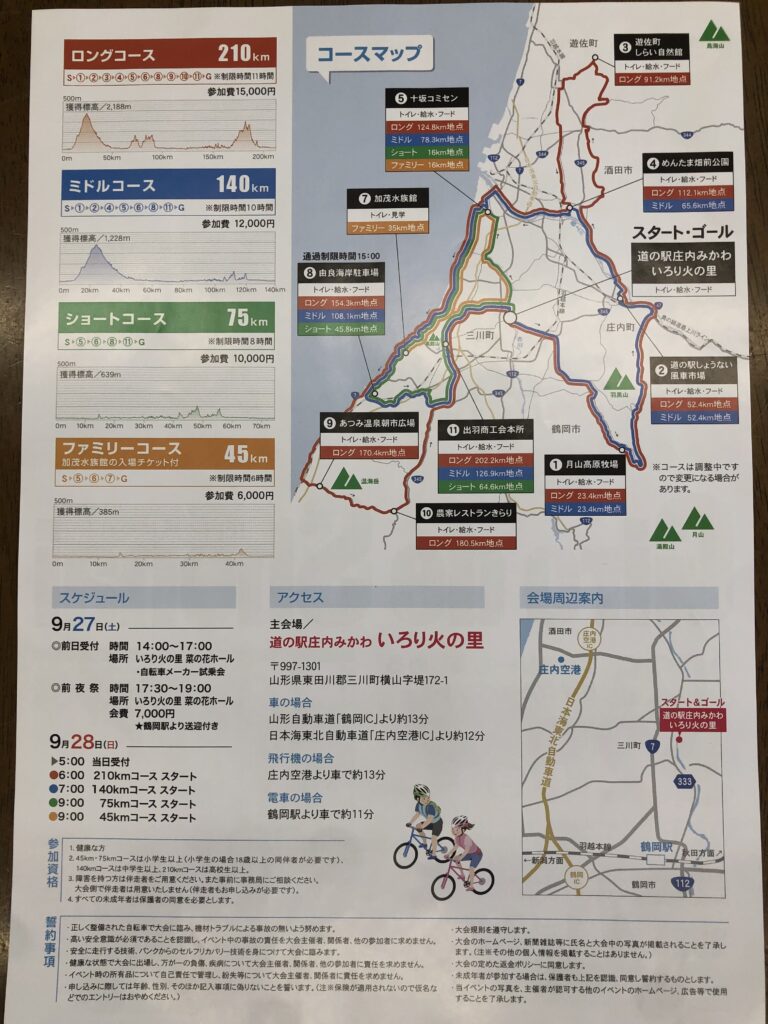今日は、7月14日(月)。
昨日 13日(日)は町会のレクリエーションとして、ボーリング大会が開催されました。
朝10時。
町会から比較的近くにあるレジャー施設のラウンド1に集合。
ロードバイク仲間であるbest岡田さん、なべちゃん、kit1002さんも参加しており、総勢は42名。
私はおそらく30年ぶりくらいになるんでしょうか、久々にボウリングを楽しみました。
2ゲームを行なってのトップは、なんと町会長。
スコアも立派なもので、300を余裕でオーバー。
kit1002さんも300オーバーの見事な入賞。
best岡田さんもまずまずのスコアだったようです。
それに続いて、私となべちゃんは…
まあ、書くのはやめにしておきましょう。
さて、午前中はボウリングを楽しみ午後からはマッタリ過ごす…
と思っていた私ですが、そこに ”ピロン”…とLINE。
「うん、誰からだろう?」
と思って見てみると、珍しくとむぎーさんからのLINE。
「今日の夜、空いてる?」
おー、もちろんです!
ということで、新盆のお墓参りに帰省していたむぎーさんと、久々に飲みに出かけました。
お互いに体に痛い箇所を抱えています。
私は古傷が痛むことに負けて、しばらくロードバイクをお休みしていますが、むぎーさんは今現在も、痛い箇所を抱えながらも、毎日のランニング&ストレッチを欠かしません。
「でも、疲れは取れにくくなった。それは本当に実感している」
むぎーさんはそう言います。
それには激しく同意します。
ただ、それでもトレーニングを欠かさないあなたは、やはり大したものです。
私は私で、現在の正直な気持ちを伝えました。
古傷になっている右膝(ひざ)を打ちつけてしまったが、
「痛みはこのまま引かない可能性がある」…
と感じている。
そうなってほしくはないけれど、痛みがあるままではロードバイクでのヒルクライム/ロングライドは、ちょっと難しいと思う。
そのときは、オートバイに乗り換えるかも。
ただ、オートバイで日本中をツーリングしても、ロードバイクでヒルクライム/ロングライドを行ったときの満足度にはかなわないような気がする。
それでも、オートバイもロードバイクと同じ二輪車。
子供のころに憧れたヒーロー ”仮面ライダー” になったつもりで、オートバイのツーリングを楽しむことにするだろう。
むぎーさんは、否定せずに私の話を聞いてくれました。
それに救われたような気持ちになりました。
ただ正直に言えば…
オートバイも嫌いではなく、チャンスがあれば乗るのも悪くはありません。
でも、制限は色々あるし、実用性は低いかもしれませんが、私にとっては自転車(ロードバイク)の方が良いですね、やっぱり。
右膝、治れ治れ…
そう思いながら右膝をさすっている今朝の私でした。